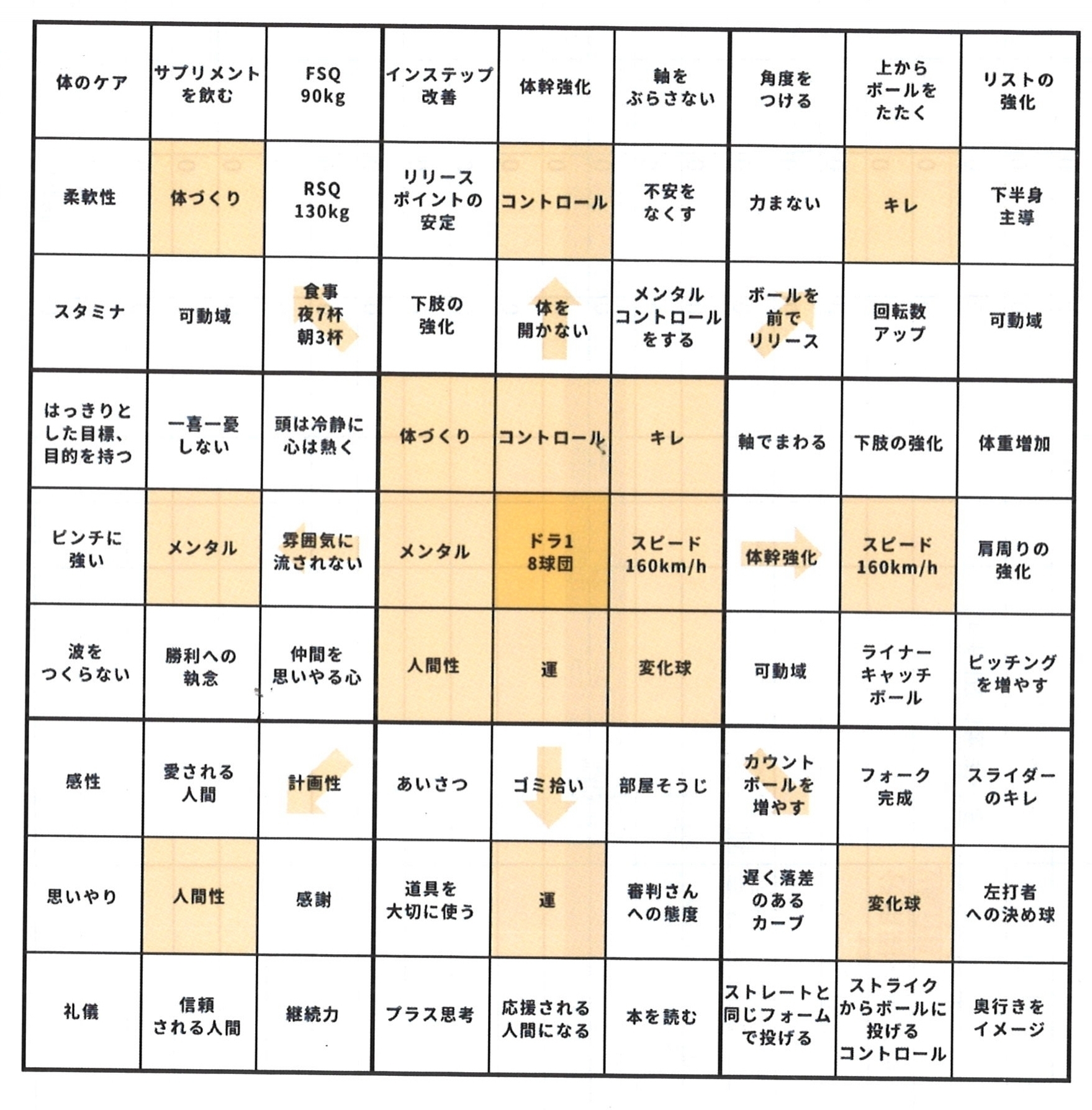ささきの木
これは誠心住工房フォレストが発信するYouTubeのタイトル名です。動画の内容は主に
「雪国に適した家づくり」となっていますが、部分的には雪の降らない地域でも役に立
つ内容も含まれているので是非多くの人に見て戴きたいと思います。
申し遅れました。私は誠心住工房フォレスト代表の佐々木利幸と申します。初めに簡単
では有りますが、私の経歴を紹介させて戴きます。
昭和59年秋田県立横手工業高校建築科を卒業後、同年渋谷に本社が有るT急ホームへ
入社。平成元年にM菱地所ホームへ移籍。平成2年にN村不動産に移籍し、約8年半東
京の大手ハウスメーカーで現場監督を経験してきました。平成4年9月に帰郷し、秋田
市のMワールドへ入社、平成19年にMの家に移籍し、この間設計業務、パネル工場の
工場長や商品企画開発業務などを経験してきました。サラリーマン人生最期の会社とし
てS友不動産の新築●っくりさんに入社し、約3年半住宅リフォーム業の営業、設計、
工事管理を経験して参りました。
平成27年4月に株式会社フォレストを設立し、木造住宅の新築とリフォームの設計・
工事請負を主たる業務として現在に至っております。住宅業界に入って丸40年になり
ますが、これまで培ってきた知識や経験を元に、これから住宅を建てられるお客様へ有
意義な情報提供をして参りたいと思っております。
さて建築業界はここ数年激動な時期を迎えています。きっかけはウッドショックですが、
コロナウイルスの世界的感染とロシアのウクライナ侵攻が拍車を掛けました。ようやく
コロナが収まりつつ有りますが、いま日本では数十年ぶりのインフレと記録的な円安で
全ての商品が高騰しています。もちろん住宅価格も例外では有りません。ウッドショッ
ク発生後から毎月のように値上がりして昨年で一旦落ち着いた感がありましたが、止ま
ぬインフレと円安が歯止めの効かない状況を引き起こしています。正直言ってウッドシ
ョックが始まった頃に住宅価格がここまで上がるとは誰も想像していなかったと思いま
す。ザックリですが、約3割は上がったのではないでしょうか?仮にウッドショック以
前に2,000万円で買えた住宅がいま買うと2,600万円もする訳ですから、これ
は尋常では有りません。私たちが手にする給料の伸び率も一律3割上がれば問題にはな
りませんが、世の中そんなに甘くは有りません。大手企業がこの春に大幅なベースアッ
プを行いましたが、国民の多くは中小企業の働き手です。日本国民が今の物価を普通と
感じるまでに、あとどのくらい時間が必要なのでしょうか?
さて話をウッドショック発生時に戻しますが、あの時にロシアからの木材輸入がストッ
プし、北米からの輸入も大幅に減り、丸太の価格は確かに上がりました。しかし、我々
に提示された木材価格の上昇率と丸太価格の上昇率には大きな乖離が有りました。
実は丸太価格の上昇率はそんなに大きくはなかったのです。まぁ言ってみれば他国の木
材事情を逆手に取って「いま上げないで、いつ上げるんだ!」という木材業界の仕掛け
た罠にはめられた訳です。その証拠にこの期の木材会社の決算は軒並み売上高大幅アッ
プで過去最高です。高値で今まで通りの数が売れれば当然ですが、問題は利益です。
何とこれも過去最高の利益を上げているのです。ウッドショックで原価が上がっている
のであれば、利益は例年と変わらないはずなのに過去最高で前年比大幅アップ!って
おかしくないですか?正にボロ儲けとはこの事です。
先述した通り、ウッドショックにコロナウイルスの世界的流行が拍車を掛け、木材のみ
ならず有りとあらゆる資材が一斉に値上がりしました。そしてその結果が現在の住宅価
格に反映されている訳です。が、それにしても高すぎると思いませんか?ほとんどの住
宅会社が坪単価80万円以上、高い処だと100万円の価格で売っています。弊社の計
算ではウッドショック前と後で約3割アップしたと考えております。仮に以前60万円
/坪で販売されていたとすれば現在の価格は78万円/坪です。ウッドショック以前の坪
単価60万円であればそれなりに品質の高い住宅が建てられました。弊社では何とか坪
単価80万円未満で良質な住宅をご提供できるよう企業努力しております。
YouTube「ささきの木」ではこれから家を建てようとする方にとって有意義な情報提供
して参ります。特に雪国にお住まいの方にとってはとても参考になる動画となるでしょ
う。また政府が提唱している「100年住宅」を建てたいと思われている方にも同様で
す。発信するまであともう少しです。是非ご期待ください。